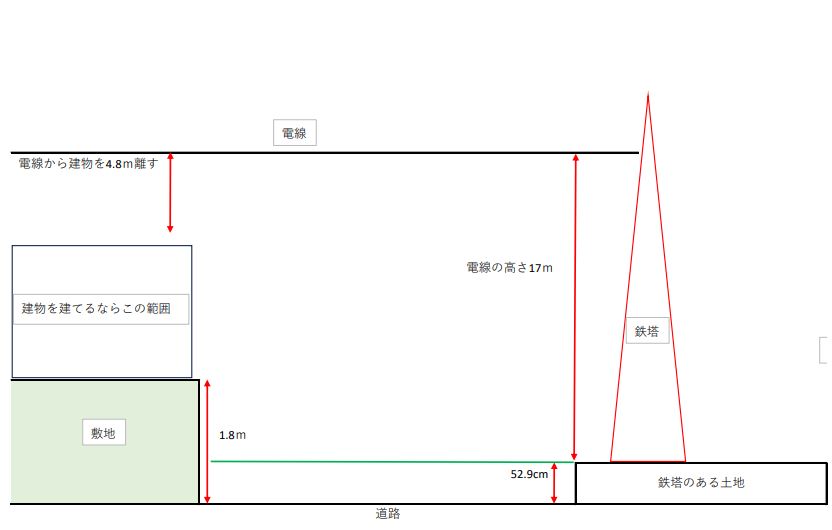先月のバレンタインデーにコロナウィルスに感染してしましました。
昨年秋口に続き、約半年ぶり2度目の感染です・・・。
今回は昨年に比べて症状自体は軽かったように思います。(昨年感染時は5日間38度台の熱が続きましたが、今回熱自体は3日目には引きました。)
問題は陰性になった後です。
昨年のコロナ感染後は、2カ月半「喘息的な咳」が続いたり、挙句今まで罹ったこともない「副鼻腔炎」、しかも急性副鼻腔炎でしたので顔半分側が痛くなったり・・・。
そして、今回も先週から妙な鼻づまりが続くので耳鼻科に行ったところ「副鼻腔炎」の診断を受けてしまいました。そしてそれとは別にやはり咳が今回も続いております。
コロナ感染後の後遺症というものなのでしょうが、質が悪く地味に辛いですね。。。 ただ、世の中には味覚が戻らない、嗅覚がおかしくなった、脱毛してしまう、常に体がだるい等々、様々な症状でコロナ感染後に苦しんでいる方々もお見受けします。
私がコロナに感染して思うのは、コロナ感染後に日常生活に支障をきたしてしまう程の重い後遺症が今も続いている方々はどのような生活をされているのか。コロナ感染後の普段の生活に係るフォロー体制(職場の勤務体制、生命保険の保険適用範囲、医療費補助・コロナ感染 等)が整っているのでしょうか?
コロナ感染後の後遺症について、最近はメディアにも取り上げられていない様子ですが、私自身も後遺症がもっと重かったらどうなっていたのか・・・?と考えることがあります。
自治体の方々、都道府県、そして、、、国会議員の先生方には是非とも継続フォローして頂きたいところです。(最後に本件と全く関係ない つぶやき:キックバックを「還付」と呼ぶのはおかしいゾー!!)