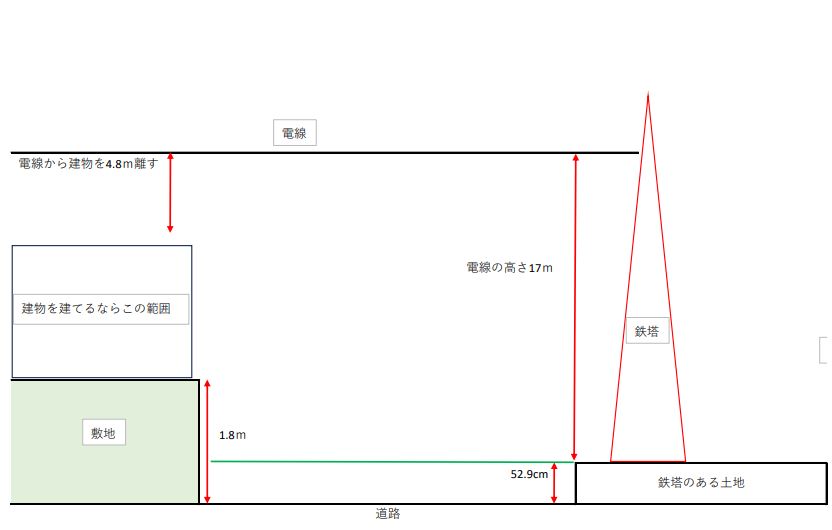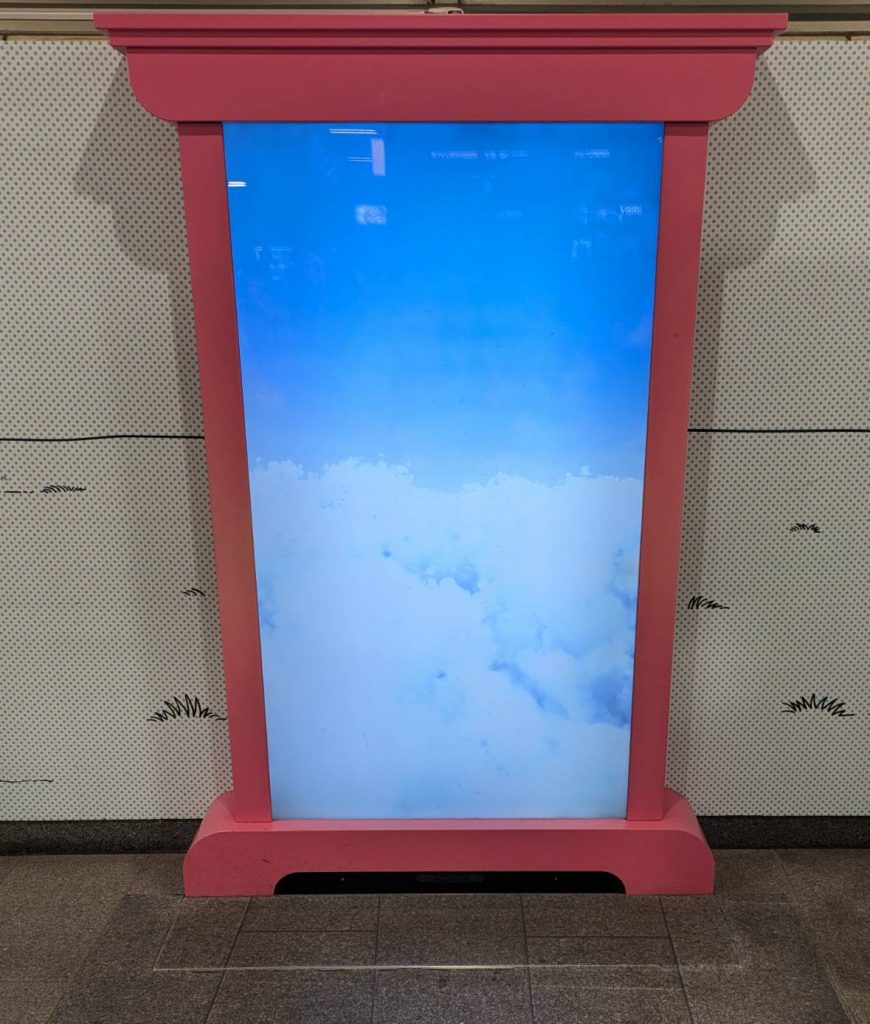こんにちわ。今年は朝夕と日中の寒暖差が激しいですね。 体調にはくれぐれも注意して日々生活しようと心掛けていく次第です。
さて、本日は国・各都道府県・各自治体からの施設整備の募集、「公募」について考えて参りたいと思います。
保育園、介護施設、障害者の方々の施設 等々、福祉施設には様々な施設があり、国や県、各自治体からの助成金(補助金)が絡む場合の新規施設整備は基本的には公募を行った上で各々の施設整備を行います。
私どももこのような「公募情報」は随時確認するのですが、たま~に「おや?」と思うような募集を目にすることがあります。
この「おや?」というのは、不信感に近い「おや?」になります。
「なぜこの時期に募集を掛けているのか?」「なぜこの規模の施設を整備するのに、募集期間はこんなに短いのか?」「この施設は今(ないし、この先)必要なのか?」・・・。
私どもにとっては、募集情報は当然大事なのですが、「おや?」という公募に関しては「探り」を入れます。
「探り」を入れる中で、その募集の背景が見えることもあれば見えないこともあります。
背景が見えるもので私どもが「納得できるもの」であれば、乗り気になります。一方で背景が見えないものや背景は見えるけど「何か腑に落ちない。」「それってどうなんだろう。」と感じるものは当然ながら口には付けません。
公募だけではありませんが、物事の背景をできる限り知ることは非常に大切かと思います。
抜かりなく本日も業務に励む次第です。